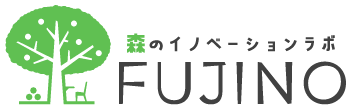藤野エリアに300人以上いるアーティストやクリエーターの活動を紹介。
今回は、第1回目をオンラインイベント、第2回目をフィールドワークと2回にわたり、藤野エリアに300人以上いると言われるアーティストやクリエーターの活動の一端を紹介し、こうした活動と地域コミュニティとの関係を解き明かしつつ、主に首都圏で働き・住む人にとって、ふらっと週末に気軽に出かけることができる藤野エリアの奥深い魅力に触れることができるイベントを開催します。
「傍嶋飛龍さんの廃材エコヴィレッジゆるゆるは、多くの方が参加して作り上げているという点でコミュニティアートの文脈にあり、横田宗隆さんのパイプオルガンの製作方法のオンサイト・コンストラクションや、現在藤野地域での様々なアーティストやクラフトワーカー、大工などと作り上げていらっしゃる活動も根底に流れる思想は近いものがあると感じています。アートシンキングやアートナビゲーターの活動をされている臼井さんのお話もお伺いしながら、アートと地域コミュニティの関係について皆さんと探っていきたいと思います。」(森ラボ コミュニティマネージャー 高橋靖典)
主催:相模原市
企画・運営:株式会社三菱総合研究所
協力:一般社団法人藤野エリアマネジメント
①オンラインイベント
日時:2021年12月16日(木)19時~20時30分
対象者: 自然地域での活動やアートに関心のある都市住民
参加費:無料(先着300人)
プログラム
■地域の紹介(10分)
■地域活動のプレゼンテーション(20分×2名)
・横田宗隆オルガン製作研究所
横田宗隆
・画家/万華鏡作家
廃材エコヴィレッジゆるゆる村長
傍嶋飛龍
■パネルトーク(40分)
【登壇者】
・横田宗隆オルガン製作研究所
横田宗隆
・画家/万華鏡作家
廃材エコヴィレッジゆるゆる村長
傍嶋飛龍
・丸の内プラチナ大学アートフルライフ講座講師
臼井 清
【ファシリテーター】
・森ラボ コミュニティマネージャ
高橋靖典
登壇者プロフィール
横田宗隆(よこた・むねたか)

1952年生まれ、東京都出身。中学生の頃に聴いたバッハのレコードに感銘し、パイプオルガン製作の道を目指す。大学在学中から国内外での修業を経て米国で独立。カリフォルニア州立大学の依頼がきっかけとなり、ヒト・モノを全て現地で調達する手法、「オンサイト・コンストラクション」に挑む。その後、スウェーデン国立イエテボリ大学の客員教授を経て、2015年に帰国し、相模原市旧藤野地区に「横田宗隆オルガン製作研究所」設立。現在、オルガン製作と並行して、後進の指導にも力を入れている。東京藝術大学非常勤講師。


傍嶋飛龍(そばじま・ひりゅう)

画家・万華鏡作家・廃材エコヴィレッジゆるゆる村長。『人生はアートだ』 画家、万華鏡作家、超音楽的お遊び集団じゃねんず団長、そして限界集落の廃工場を廃材で作り上げている『廃材エコヴィレッジゆるゆる』村長と遊びに本気の多動症マルチアーティスト。廃材エコヴィレッジゆるゆるは様々なエコシステムを廃材で作り上げ、「コミュニティー通貨ゆーる」の導入や、狩猟採集イベント「ビストロ山」「天才合宿@藤野」などライフスタイルやコミュニティーづくり、意識改革など既成概念を壊すイベントを企画している。多摩美術大学絵画科大学院卒業。第1回池田満寿夫記念芸術賞、第1回利根山光人記念賞で大賞を受賞。

臼井清(うすい・きよし)

合同会社志事創業社(しごとそうぎょうしゃ)代表。諏訪精工舎(現・セイコーエプソン)にて国内外でマーケティング、現地法人でのトップマネジメントなど歴任する一方で、社会起業家との協働によるプロボノ活動にも参加。2014年、ビジネス創出やキャリア開発に向けた“学び”をプロデュースする「志事創業社」を設立し独立。「人生100歳時代、幾つになっても進行形」(Age100.ing)をキーワードに、事業開発や顧客開拓のサポートを中心に「新チャレンジ」のコンサルティングを手掛ける。認定アートナビゲーター(美術検定検定1級)として、アートシンキングのビジネス応用にむけた様々な活動を推進するなど、活躍の巾を広げている。一般社団法人新興事業創出機構(JEBDA)フェロー,中小企業大学校講師,丸の内プラチナ大学設立メンバーでもある。
高橋靖典(たかはし・やすのり)

藤野エリアマネジメント代表理事。神奈川県相模原市旧藤野町在住。 子どものシュタイナー学園の入学に伴い藤野に移住。持続可能なまちづくりを目指すトランジション活動に参加し、地域通貨や地域電力など、様々な地域活動に携わる。近年ではアーティストやクラフト作家のシェアスタジオや、ソーシャルビジネスのためのシェアオフィスを運営する藤野エリアマネジメントの他、農泊施設やレストランを運営する農業法人 藤野倶楽部顧問や、 学校法人シュタイナー学園理事長なども務めている。
横田:
私はパイプオルガンを作るという特殊な職業をやっている関係で、オルガンはどういうものかという話をすると長くなりますので、私がどういう風にオルガンに興味を持ったのか、自己紹介的な意味も兼ねて、お話しさせていただきます。
幼少期にピアノを習っていてバッハに興味を持ち、興味を持つどころか狂ってしまった子供だったのですが、それから派生してキャンバルとかオルガンを好きになりました。
オルガンは特に、14歳の多感な時期にオルガンが私の心を洗ってくれるような経験をしたので、それからオルガンに首ったけというような人生でした。
オルガンは当時日本にあまりなかったので、もう半世紀以上前のことです。レコード、いわゆる昔で言えばディスクですね、それで聞くしかなかったのですが、お金のある限り買いあさりました。それで聞くと、300年250年前に作られたオルガンの音がなぜかすごくいいのですが、現代のオルガンは非常に面白くない。何もわからないながら、自分で感動できないものをもどかしく思っていました。
そういう経験をしながら大学時代学生運動の終わり頃、社会改革にどのように自分は関われるのか真剣に考えました。私自身は直接関わったことはあまりないのですが、何かやらなきゃという焦りのようなものがあり、自分が最も得意であり、好きなものに進みたいと思い、社会のためになるつもりでオルガンを作り始めました。
非常に長い修行を必要とする伝統的な芸術ですが、オルガンを生業にしていくには、現代のオルガンを作って売っていかないといけないのかなと思いきや、あるドイツ人の有名な演奏家であると同時に古いオルガンを修復して蘇らせる、修復の監督官をやっていた人に二十歳の時に出会いました。
彼は、古いオルガンがいかに美しいもので、それを現代に蘇らせることになんの躊躇もなくその価値を力説してくれました。それだったら自分は趣味とかでなく仕事でできるという確信を持ちました。古いオルガンの作り方で、新しいオルガンを作ること。これはオルガンの業界でも社会変革ということですね。現代では工場で生産して、パーツメーカーもあり工場で作った後出荷して現場で組み立てる、そういう形でオルガンは作られます。
日本で見習いを3年、辛い修行でした。大卒の同級生は私の給料の3倍くらいも取っていましたけど、とにかく腕に技術をつけるのだと言い聞かせて我慢して、お昼を抜いて練習をしたなんてことも1年くらいありました。そのようなほぼ全ての領域を回って見習いを3年やりました。
ただ、非常にいい先生だったのですが、やはり機械を使って現代風に作るわけですね。私自身はどうしても手で300年前に職人たちが作ったような作り方で楽器を作ってみたいと思っていました。
これは最初の楽器です。注文を取らずに作り始めて、ジリ貧状態で借金を抱えましたけれども、この楽器を作ったら上野学園大学の先生が非常にいい楽器だとして買い上げてくれました。これが私のその時の結婚費用、それからアメリカに行く交通費、アメリカで家を借りて資金礼金みたいなものを払って、そして自動車を買ってまだお釣りがある。
そんな形で私はこの道に入ったわけです。これは全て手作業で作った小さな楽器ですが、1978年のことです。
その後アメリカで修行を5年しまして、その時の先生は世界的に20世紀有数の非常に優秀なオルガン製作者でした。非常に優秀な方なのですが、彼もクオリティと経済、生活のジレンマが非常に強くあった人でした。現代最高峰の人でもまだ300年前に至らないと彼は感じていたようです。追求をすればするほどお金がなくなっていく、そういう状態を目の当たりにし、何か技術だけじゃない、そんなにお金がいるんだったら、実際現代の楽器は300年前と比べると6分の1の値段で取引されているそうです。その状態で300年前のようないい楽器を作れるのか。それを真剣に考えた時、経済力がなくてもできる、何か環境づくりがあるのではと思いました。
見習い中に訪れたヨーロッパの風土は、古いオルガンは山一つ越えればその土地の文化と直接密接に結びついているわけです。私が旅したのはドイツでしたが、街が違えばビールも違う街が違えばソーセージも違う、それぞれの土地にある土着のソーセージの味、ビールの味っていうのが非常に印象に残っています。
それと同時期に、和歌山の祭りの本を読み、あるいは高山に行き、友人がいたということもありますが、そこで学んだのは、どんなに貧乏な街でもあるいは村でも、祭りにかける情熱は非常に強いもの。1年に一度のお金にならない祭りのために一年間嬉々として準備をする、仕事をする、仕事も辛いことだったのでしょうが、祭りがあるから生きていけたということが呂律にわかるお祭りの背景ということですね。
さらにはヨーロッパの中世のオルガンを作っていた人たちのことを考えますと、まず初期には、修道院で、修道院は今で言えば大学のようなところですね。修道僧が当時必要だった農学、科学、文学、そういったものと同時に音楽、それから楽器を作るということが研究され、実践されていたわけです。それらを行なっているうちに、専門の修道士たち、オルガンをつくることに長けた人たちが専門家として一つの修道院でオルガン制作を指導して楽器が出来上がるとまた次の修道院に行って楽器を作ると、そういった形で楽器が作られるようになりました。
中世も後期になると、職業的なオルガン製作者が現れました。しかしその人たちは、今のような仕事場で楽器を作るのではなく、仕事が入ると教会に出向いて教会の中で仕事場を作るのです。オルガンという楽器は大きいですから、当時の道路事情などを考えると、遠くから壊れやすい楽器を馬車で持ってくるということは非常に不可能なことだった。そこで、教会に移り住んで仕事場にしてしまうという作り方をしていました。教会員は街ぐるみですから大工もいれば指物師もいる、近郊氏もいる、彫刻家も画家もいる、そういう人たちが教会員な訳です。彼らは彼らがキリスト教でいう神に与えられた技術なり感覚というのかな、それをまた教会、神のために奉仕するという形で楽器を作ったわけです。オルガン製作者がそれを指揮していた。それらを製作中に支えていたのは、教会の中の農業に従事する人たちであり、あるいは商業に従事する人たちは外から買わなければいけない金属などを調達していた。もちろん色々な記録があり、食べ物などをオルガン制作中に製作者たちに供給したという記録もあります。そのような形で、街ぐるみのオルガン作りが中世で行われていた。これは、祭りの存在と中世のオルガン作りということは私の想像力を書き立てまして、これを現代でやってみようと、
それを最初に行ったのは、カリフォルニア州立大学、北部のカリフォルニア、サクラメント市のそばにチコという街があります。これ(写真)はカリフォルニア州立大学チコ校舎と言いますが、そこの100年祭にオルガンを作ろうということで、私がアドミニストレーターとして招かれ、アーティストイングレジデンスという形ですね。
これ本当に町ぐるみでですね、その町にある商業に関わる人たち、例えば、3・4階建を作るくらいの材木を寄付してもらいました。それから、多くの人たちに寄付してもらいました。アメリカの大学は寄付を募る専門の部署があって、何十人もの専門家が寄付を募るのですが、もので寄付を受けたり、あるいはお金で寄付を受けたこともあります。それから、私の発案ですが、街の仕事がなくなったお年寄りたちを探し、昔やったことがあるような人たちから色々な援助を得たのです。彼らは彼らで、週に何回か仕事場に来て昔話をするのが楽しくていらしてくれたのかもしれないですが、だいたいオルガンは非常に大きな楽器ですから、いろんなところを作らなければいけない。そして、いろんな経験を持った人たちが必ず何かの形で関われる。そういったプロジェクトなのですね。彼らは本当に楽しんでやってくれました。他の仕事場で、今の現代のオルガンの仕事場でかなり辛い仕事を安い賃金でしなければいけないような、みんなひしゃげた心で仕事をしているのですけれども、そこでは、全く違う雰囲気で、みんなが嬉々として仕事をしてくれました。まさにしてやったりという感じですが。
もう一つこの後でカリフォルニアの中で、今度は教会で同じようなことをしました。そこでは、教会員がいろんなことを助けてくれましたけど、今一つ覚えているのは、ある主婦の方が、普段はテレビを見ながら編み物をする、でもオルガンの中のある木製のパーツを作ってと頼んで、それができたらこんなによくできているパーツはどこに行っても見たことがない。そのおばさんが言うには、私の家族はこの教会に何代も前から、そして私の息子たち、娘たちが何代も何代もこの教会に行くことになるだろう。その時におばあちゃんがこんなの作ったからこんなオルガンになっちゃったよって絶対に言われたくないから本当に頑張って、テレビを見ながら子育てしながらそう言うパーツを作ったのだという話を聞きました。それは未だに覚えています。
そして、作り方、環境というのは非常に特殊なものだったわけですが、この楽器が非常によくできたと評価され、ヨーロッパに招聘されました。
スウェーデンのヨーテボリ大学というところで教授として呼ばれて、そこで大きなプロジェクトを指揮することになりました。これ(写真)は非常に大きな楽器スウェーデンの国立銀行から6年間の研究費がでて、これは、町ぐるみというものではあまりなかったのですが、私はヨーテボリ大学に属していましたけれども、同じ町にチャルマース工科大学の六学部の科学者と一緒に300年前のオルガンというのはどういう風に作られていたのだろうかということを科学的なレスを入れながら研究をしました。その研究の指揮をし、自分で設計し、楽器を仕上げて、こういった大きな楽器ができたわけです。これは地域のボランティアとは全く違うレベルでの共同作業を学際的な共同作業でした。ヨーロッパで私のような日本人がこういったものを作るあるいは古い楽器の修復も随分かかりましたけれども、日本人が、法隆寺の再建を外国人がやったら変な気持ちになる、そういった風に扱われたと思います。ですから、かなり頑張りました、ただ、日本人としてはですね、貢献できることもいくつかありました。例えば当時の西洋では、結果としての形の重要性、ユネスコが保護しているもの、そういったものが多かった。今でこそ、無形論のものに対する尊敬の念が非常に高くなりましたけれども。日本における、式年遷宮の概念とか、制作過程、作る人の姿勢、精神の復興作る側の心の問題ですね、そういったものを復元する。これはそういったプロジェクトは古いやり方を通して初めて心自体がどういうものだったかということが見えてくるのですね。それを考えてきたと思います。
これ(写真)はニューヨークのコーネル大学のチャペルで作ったもの・・・
(写真)昔の工法というのが特徴的なことが書いてあります。
手加工なので、加工度が少ない。自然にあったものがわりあいそのまま使われる。例えば、木は下が太くて上が細いです。それを逆に交互に組み合わせると、平らな、平行な板ができます。そういう風な形でやっていく。今の工法というのはペーパーになった木をまず平行に切ってしまう。無駄なものとして。そういう無駄が出る。昔の方法はそういうことではない。そして手に入った材料に合わせて加工、あるいは加工どころではなく、デザインの実際に手で持った時、あるいは拳骨で叩いた時、その音がどういう風になるか。木というのは芽がありますからそれを切ってしまうと音が伝わらない。加工を少なくするというのは芽あげがないので必然的に強くしなやかであり、同時に音響的にも音がよく伝わる。職人一人一人が材料に合わせて変えながら作っていって、設計者であり、加工者である。これは、今の若い人たちがこういう職場に入ってきて、なかなか面白いと思わないのは、全てのデザインが設計室で終わってしまうからです。設計室でデザインをする設計者がいて、それをやるためには、材料も予測可能なものでないとデザインができないのですね。昔のものというのは、大まかなデザインは作ってありますが、実際に生きている生の材料を見ながら、実際に職人たちが考えながら、多少即興しながら作って行くわけです。それを実現したかった。そういうものを通して、独自の様式が出来上がる。その土地の材料を使うということはもちろん、気候的に適合し、将来壊れたとしても同じものが手に入りやすいと。その土地の人で作るということは、自然にその独自の様式が出来上がることになります。
それから昔の加工法の特徴として、木材なら木材の全てを使う。良いところはオルガンの前面に使う。汚いところはそういう必要なところに使う。日本のクジラの食べ方のような木材の使い方を、今は絶対にしません。一番良いところだけ全部とって、細かく裂いて、糊付けして、綺麗な材を、狂わない材を作ってそれで楽器を作ってしまいます。そういう風に作られた、もちろん材の見方を知らないといけないですが、我々が古い楽器の中に入った時びっくりしたのはそういった視覚的な〜〜ですね、良いものと悪いものが全部混在して、機能的に良いところに使われている、見るだけでダイナミックです。それから、糊の寿命に頼らない構造を作る。組手などですね。それは日本の建築ですけれども。そういったものを通して、全ての仕事を終え、日本の方に帰ってきました。
帰ってくるにあたって、藤野を選んだのにはいろんな理由がありますが、もちろん、今日の主題である地域の工芸家たち、その人たちのおかげでかなり難しい楽器を作ることができました。その最初の楽器が宮崎の(写真)日本福音ルーテル宮崎教会ですね。2019年に完成した楽器です。この製作者のリストを見ると、半数以上、60%ぐらいが藤野の現地の人です。それから次の、これ(写真)はですね、青少年の教育のために組み立て可能な、2時間で生徒たちが組み立てて、音楽を奏で、オルガンの作り方も勉強できるというものです。それを意図して2020年に作ったのですが、これを使って、相模原市の公立の小学校あるいは中学でそういったイベントをやりたいと思っていたところがコロナとなってしまい、今まで実現しませんでしたが、来年の三月に相模原市のアートスフィアという助成金をいただいて藤野芸術の家でそれをやることになっています。そういう形で私は地域を巻き込んできたわけですが、結局はクオリティにクオリティを求めて、そのために地域の人たちが関わると、そんなに高くなく、お金を使わずに、安く使うという意味ではなくてですね、みんなの熱気とそれから近所にふらっときてふらっと仕事をしていただくこともできるので。それとその土地の色合いがよく出るということですね。そもそもオルガンという楽器は教会にあった楽器で誰もが行けるところ、コンサートホールのようなアリストクラットが行くところではありませんでした。オルガンを作る人たちも、そういった宗教的な確信を持って楽器を作っていたわけですけれども、そのコミュティー精神のようなもので、やっぱりみんな大きな楽器に何らかの形で関わる楽しさを味わっていただけたと思います。そういったことを続けて、やっぱり楽器ですから、音楽を通して真に人に語りかけるものをこれからも作り続けて行きたいと思っています。
画家・万華鏡作家:傍島飛龍
傍島:
僕自身、実は父親が技術の版画の作家で東京芸大を出ていて、男四人兄弟で、僕は次男で、兄弟みんな芸術家だったりするんですけど、そんな美術一家に育って、子供の時僕自身多動症の問題児今ではADHDと区分されてしまうような、席に着いてられなくて授業中走り回って先生を困らしていたタイプだった子供で、唯一絵を描くのが大好きで、絵を描いている時だけは席についているみたいな幼少時代を過ごしていて、絵を描くと褒められるから、自分は絵を描く人になるんだみたいな感じで育っていって。高校は勉強できなさすぎて農業だったらいいやといって農業高校へ行き、その後、技術大学に進んでいって、絵の世界に入って行きます。
大学に入った時に、大学教授が言った言葉が最初突き刺さった。「これからは、あなたはあなたの表現をしてください」と言われ、「以上!」みたいな感じで、あとは版画の科だったんですけど、「版画の技法は教えますから、あとはあなたを表現してください」と言われた。
あなた、つまり、私って何だ、とすごくその時考えるようになり、それまでは漫然と描きたいものを書いていたのが、それは自分なのかという問いが生まれてくるみたいなところがあって、自分って何だ自分って何だと思いながら画面と向き合うことを大学時代はしていました。
今出ているもの(写真)は、大学院生の時の作品なのですが、もともと、モノクロの全然違う絵を描いていて、これって自分かもしれないというモノクロの風景画を描いていたんですけど、それを、実はいろんなコンペとか出したり大学一年生の時にしてて、海外のミニプリントの版画のコンペを出したら、入選したりして、その作品自身評価はされるし、これが自分かもしれないな、自分なのかなと思っていたら、大学二年生くらいの時に池田満寿夫(?)さんという絵描きさんが特別講義で現れて、池田満寿夫さんの講義が終わった後、自分のモノクロの作品を見せた時に、池田満寿夫さんが言った言葉が、「これは完成されすぎていてつまらないから今すぐやめなさい」と言われて、私かもしれないと思って作っていた作品を今すぐやめろとはどういうことなんだろうと思って、憤る自分がいたり、いやでもそうかもしれないという自分がいたりして結構また、私って何だみたいなことを思いながら画面と向き合っていて、モノクロの絵を捨てられずにいる自分と、もっと壊したほうがいいんじゃないかという自分が葛藤する時期が始まって、最終的にモノクロの絵を池田満寿夫さんが言っていた意味がわかってきたと思って一回やめて、そもそも絵を描く根本に戻らないとダメだなと、私はなぜ絵を描くんだろうかみたいなところに戻りたいがために、幼稚園生の頃の絵を実家から引っ張り出してきて、それを見つめながら大学院生の時に画用紙にずっと絵を描き続けるということをやっていた。それが、私と絵との向かい合いの時期で、そのまま落書きのような絵を拡張していった作品が、今画面に写っているもので、池田満寿夫さんがそういう言葉を言ってくれたから、そんなところに行き着いたところがあって。
大学院2年生の時に池田満寿夫さんが特別非常勤で特別講義できていただけだったのが、多摩美大の版画の大学教授になるという話があって、とうとう作品が、自分がぶっ壊した後に、捨てた後の作品を見せられるなと思っていたら、池田満寿夫さんがなる1ヶ月2ヶ月前に突然なくなってしまって、作品を見せられないということになって、あれーと思っていたら、第二の次世代の池田満寿夫さんを発掘するみたいな感じの池田満寿夫記念芸術賞というコンクールができて、第一回に応募したら、僕がグランプリだった。この写真の作品が、グランプリを取った作品です。
作品で大きな評価を得て画商さんがついてみたいな形で画家業が始まったんですけど、大きく自分が満たされるかなと思ったら意外とまだ苦悩が続いて、もっといい作品を作らなきゃという思いもありつつ、承認されたら自由に描けるのかと言ったら全然そんなことはなく、精神的に病んできていた。その中で23歳くらいの時に、人工物を見ると気が狂いそうになっていて、たまに散歩して山の中に入っていたんですけど、そもそももう山の中に暮らしたほうがいいかなと思った時に、実は、芸術の町藤野っていうのがあるらしいよということを聞いて、とりあえず行ってみようという感じで家を決めて、移り住んだのが25歳くらいの時でした。
藤野に移住してから絵描きの活動をして、僕は基本、下絵を描かずに即興で絵を描くんですけど、そんな絵をたくさん描いて画家業をしていたところ、藤野に移住したらお隣さんが第一移住世代の方で藤野自体が30〜40年前くらいから芸術家の移住が始まったみたいな歴史があって、その方にお話を聞いてたら、いろんな藤野に面白いアーティストがいるよと言われ、その集まりに参加したりとかして、そして自分自身はすごく絵を描くことって孤独に家にこもって作品を作って、ギャラリーで発表するみたいなスタンスそういうアートみたいなことをやっていたのが、宴会に行ったら、ミュージシャンが、みんないろんな活動木工とか陶芸家とかグラフィックデザイナーとかいるんだけど、酔いが進むとみんな音楽始めるみたいな、あれ、なんだか皆醸し出して楽しそうにやっていて、その時僕が認識したのが、音が鳴り始めた時からアートが始まっていると思ったんです。時間のアートだな音楽って、みたいなことをちょっと思って、それまで自分は、絵画は描いている時がアートだし、もちろん見る人もアートしなければいけないんだけど、音楽は鳴り始めた時からアートが始まっているのがすごく面白いなと思って、自分も音楽やりたいと、時間のアートをやりたいと思って始めたプロジェクトが超音楽的お遊び集団ジャネンズと言ってみんなに楽器を渡して素人オーケストラをやるというプロジェクトを始めました。
50〜60人分の楽器を集めてきてみんなに渡して、僕はジェスチャーだけで指揮をするという素人オーケストラ。だからみんな素人でもプロも混ざったりとかしてみんなでセッションする時間、音楽を作るっていう時間のアートをちょっとやりたいと思って。このジャネンズというプロジェクトは藤野でもいろんなお祭りで出演したりしてて、僕は10年ぐらいこのプロジェクトをやっていたんですけど、フェスティバルも良かったんですけど、そのうち僕自身アート思考で、この時絵描きもやってて、作品って自分の魂の投影だと思って、魂が磨かれないといい作品も描けないし、いい作品の見方もできないなと思って、そういう意味では、もっと魂が磨かれるような体験がしたいと思い、お祭りも結構出演したんだけど、お祭りをやるのが得意になってしまって、もっと僕の好きが理解できない、見てないことをやりたいと思って、福祉の業界とかで音楽のワークショップをやるようになったりもした。福祉だったり、幼稚園生や小学生、思春期で難しい中学生とか、緩和系医療の病院とかいろいろなところに行っていろんな人たちと関わって、その関わりの中から自分自身、心で何か味わい感じるっていうことが大切だと思いながら、自分のできる音のアートの時間をみんなに感じてもらいたいみたいな感じでジャネンズという活動をしていました。
幼少時代にあれだけ絵描きになりたいと言っていたのが、音楽を始めたりして、絵という一つのものに執着しすぎていた自分がいて、音のアートを知った時に、そもそも絵だけにこだわらなくても音楽も初めているし、いいなと思って、一回絵を手放しちゃおうと思って、30代頭くらいで画商さんに僕絵描きませんと言って、いきなりやめてしまいました。
そのあと実は万華鏡作りにハマってしまって、面白い万華鏡に出会って、自分も作りたいってなって、立体を作りたいという欲望もあったりとかして、自分の創作的なイメージと万華鏡という工芸との組み合わせ、あまり万華鏡の世界というかにないものを作りたいと思って、万華鏡作家になっていきます。
こういう立体系の、実は陶芸の陶器でボディを作ってステンドガラスとかそういったもので仕上げていくんですけど、実際これは、藤野に移住してきていろんな陶芸家さんと知り合ったりとか、あと藤野芸術の家というところでスタッフとして働いたりしてそこで陶芸の技術を覚えたり、あと本当にプロの陶芸家さんがいるから、こういう表現をしたいんだけど、どうすればいいですかとすぐ聞きにいったりしたら、いい陶芸家さんとかはこうやってやるとその表情出るかもよとか教えてもらったりとかして、この作品ができていったという感じです。万華鏡作家は未だに続けていたりします。
こういうガラスを溶かして映像になるものも作ったりとかしながら作っています。
これがいきなりさっきも紹介してもらったプロフィールで廃材エコヴィレッジゆるゆる村長をやっている、まあ、聞いても何が何だかわからないような内容ですが、僕自身絵画をやっていて音楽活動して、万華鏡のこともやって、震災があって、3.11があって、環境問題とかエネルギーのこととか自分自身のライフについて本当にいつ死ぬかわからないなと思って、自分自身もっと思い切って生きて良いのではないかと思って、一応藤野芸術の家というところでアートのスタッフをやっていたのですが、それも思い切ってやめて、もっと思い切って生きてみようと思って、日本を車で旅したりして、里山型の場作りをしている人に会ったり、廃材で家を建てている人に会ったり、世の中、面白い人たくさんいるし、面白く生きている人いるなと思って、またそこでさらに刺激をもらって、そもそも自分も場所作りみたいなことにすごく興味があって、場作りしたいと思って場所を探していたところ、僕が住んでいた藤野の綱子という集落のど真ん中にあった、もともと鉄工所だった廃工場がそのタイミングで売りに出されて、最初売地って見たときに撮った写真です。
これをもう買い取っちゃおうと思って、思い切って買い取って、震災後に、廃材で家を建てているファミリーに出会った時に、世の中廃材であふれているし、それに価値を与えることができたら、バブルが起こるよと、そうなんだと思って、廃材ってどうやって集めるんですかと聞いたら、情熱さえあれば集まると言われて、情熱かー割と自分ある方だなと思って、それで実は土地買うのにほとんどお金使い果たしちゃって、あとは情熱でどうにかなると、ほとんど丸腰でインパクトドライバーと丸ノコぐらいしか持ってなくて、このプロジェクトがスタートしていきます。
何もないような廃工場に廃材を集めて情熱だというのは、ある意味近場の色々な製材所とかいらないような材木が積んであって放置されているところとかそういうところにどんどんピンポーンっていってすみません、こういうプロジェクトやっているんですけど、あの材木ってもらえたりしませんかというのをどんどんやっていったら、どんどんもらえるところが増えてきて、古民家解体しているから一棟分持っていって良いよとか言われたりして、そういうのをどんどん集めていって、本当に材木買わないでできちゃうかもなという感じで、プロジェクトが進んでいきます。
SNSで情報発信しながら、実は理想を語りながらみんなで一緒に作っていこうみたいな感じで、廃材で秘密基地、僕自身実は小学校の時林の中で、森の中とかで作っていたんですけど、まさか40近くなってやるとは、そこをやっちゃうのが多動症の僕なんですけど。こんな感じでいろんな人が集まってプロジェクトが進んでいくという話です。
全国から、情報発信していたらいろんな人が集まってきて、なんか変わったことをやってる人がいるよ、変わったプロジェクトがあるよみたいな感じで、オープンするのに実は4年かかって、材木は一切製材所とホームセンターでは買わなかったという形で、この摩訶不思議な廃材の建物が、秘密基地が出来上がっていく、それが、仲間たちが本当に集まって作っていたということもあって、それがゆるゆる村民という名前をつけて、通い型の村作りプロジェクトみたいな感じのコミュニティが作られていったという感じです。
今現在の状態です。最初の方の写真と比べると、だいぶ変わっていているのではないかなと思います。地元の方も、僕自身、プロジェクトをやる前に自治会長やってたりとか、地域とも結構関係があって、なおかつ、藤野って、アーティストがもうすでに入っている、芸術の村って言われているから、わりと地元の方も芸術家さんに免疫があるというか、僕みたいに変わった人間に対して芸術家さんはやっぱり変わったことやるからね、頑張って、みたいな感じで差し入れ持ってきてくれたりとかして、そんな感じで、集落の真ん中に摩訶不思議な建物ができたという感じです。
これは中はこんな感じになっているんですけど、集めた廃材でなぜか紅白幕がきちゃったりとかして、鹿の剥製が一頭来たりとか、ツキノワグマの剥製も来ちゃったりとか、廃材ってジャンルを問わず集めるとなんでもありだなみたいなあって、それを一つアートなデザインで配置していって、建物全体がほとんど99.9%は廃材で摩訶不思議な建物を作って、そこに仲間たちが集っていくみたいなそんな感じの場所になっています。
これはステージがこんな感じになっています。ステージがあって、音楽も、ミュージシャンがライブしたりとかもできる場所になっています。
廃材コベリチがある程度建物ができてきたら、コミュニティの仲間たちが集まってなんかこういうことやりたいああいうことやりたいみたいな話があって、竹細工やりたいという話があって、竹細工部作ろうみたいな感じで、竹細工の部活が、地域で使わなくなった真竹の竹林、竹やぶは全国的に問題になっている話なんですけど、これをみんなで有効活用できるメンバーを作っていこうみたいな感じの竹細工部が立ち上がった。
これも竹細工ですね。
地元の高齢化が進んでいて、耕作放棄地が増えてきた中で、集まっているメンバーで畑やりたいという声があって、じゃあ地域の人からお借りしてやろうかみたいな感じで畑をやるプロジェクトが立ち上がったり。
あとは、みんなで太鼓叩こうみたいな、叩きたい人が集まって太鼓を叩く部活が立ち上がったり。
なおかつ、僕、すごく村づくりが面白いなと思っていて、村文化、なんかNHKかなんかの、うちにDVDで「ふるさと伝承」というものがあるんですけど、そのDVDが120箇所くらいの各地域でいろんな文化が伝承されているっていう、もともとルーツは同じようなルーツできているものも、例えば、神様にお風呂を入れるという風習っていうのが、地域によって解釈がどんどん変わっていて、普通にいいお湯を沸かして入れる地域もあれば、三日ぐらい煮立てて神はぬるま湯には入らんみたいな感じで、グツグツ煮てお面かぶって、神が入ったあとビチャビチャみんなにかけるみたいなことをやっている村もあったりとかして、村文化って小さくなって、なおかつ神様がいたわけじゃなくて、誰か言い出しっぺがいて始まったっていう、人間のカルチャーの作られ方にすごく興味があって、それめっちゃアートだなと思って、自分自身もゆるゆる村はどんなことやろうかなと思ったら、割とこうおふざけしがちななんで、パンスト相撲大会という、写真のような大会が開かれたり、これも一応、うちの仲間のOLの村民の廃材のパンストを集めてやっている大会が開かれた
あとは、全身白塗りになるお祭りを作ってみたりとか、奇祭づくりみたいなことを仲間たちでやって、おふざけしています。
ある意味、廃材っていうものは、誰かが価値がないって思ったものであって、それに対してこっちはアートの目線で価値のあるイメージができれば素材に変化する、それがすごく面白いなと思っていて、僕らがやっている住宅とか、住まいもこれからの時代、不動産ではなくて可動産でいいのではないかと、今はリモートで仕事もできるし、みたいな感じで、トラックの後ろに家を作ろうという企画もやっていたりします。こんな形で廃材コベリチでは10台くらいみんなが自分たちで作るモバイルハウスと呼ばれているんですけど、そういう動く家プロジェクトもやっていたりして、実はうちの集落に動く家に住んでいる若者が何人かいたりとかして、限界集落の中に家は貸してもらえないけど、空き地貸してもらえたらぶらっと若者がそこに滞在できるみたいな感じで、そういう方たちが、地域の人も一応紹介したりするとそういう若者が今来ているのねみたいな感じで認知されて、地域清掃とかに参加したりして、こういうアプローチの、地域に対して人口の増やし方もあるんだというところも感じつつ、家の常識なんぞやみたいなそんな感じのプロジェクトもやっています。
僕そもそもは絵画やって音楽で時間のアートを感じて、最近思っているのは、人生そのものがアートだなと思っていて、この世界自体が大きなキャンバスで、それをみている私、みんなそれぞれっていう。絵画って絵という作品を作った作家がいて、みている人もアートしないといけないのです。みんな心がアートしているんです。それぞれが違う認識で見ていたりするんです。それってめちゃくちゃアートだなと思っていて、この世界そのものも全くそうじゃないかと思って、その認識に対してアプローチするような自分たちは廃材コベリチの中の一つ、芸術の中の劇場みたいなものでそこで関わったりした人が何かを感じるようなそんな場づくりみたいなことが、廃材コベリチゆるゆるというプロジェクトでやっているという感じです。
高橋:ありがとうございました。
ここからですね、プラチナ大学のアートオブライフの講座の講師をしていらっしゃる臼井さんにもお入りいただいて、パネルトークという形で進めていければと思っております。
少し、冒頭に臼井さんのご紹介もさせていただければと思いますので、スライドを出させていただきます。
臼井:今日、どっちかというと異端児的に来ているのかもしれませんけど、ガチガチのビジネスの人間なんですけど、それが書いてあるのがこれです。
とは言いながら、次に行っていただいて、実は私はいい先生にめぐり会わなかったので、実は絵が大好きだったんですけど、高校で一旦足を洗いました。30年くらい経ってからロンドンナショナルギャラリーに行く機会があって、そこで子供達と先生の様子を見ていたら、やっぱりアートいいなと思い出して、そこから改めて、今度は創作ではなくアートで触れ合うことをやりたいなということで、今に至っています。
今、プラチナ大学のお話をしていただいたんですけど、プラチナ大学というところでアートに関するコースを設けているのですが、プラチナ大学自体は2015年に、三菱総研さんとかと一緒に始めた取り組みでして、どの年代も人生プラチナに輝くというのが大事ですねという中で、一番プラチナに輝いていない大手町丸の内有楽町の世代はどこだといったらちょうど私のいた40、50代くらい、特に50代後半のおじちゃんたちかなということで始めました。
ただ、幸か不幸か色々な方に集まっていただいたのですが、いつのまにかあそこのプラチナ大学は爺さんの大学だよねみたいな話になってしまい。けれど、どの世代にも来ていただきたいということで、そういう意味でいろんなコースを、バリエーションを増やそうよということで、増やしたのがアートのコースなんですね。このアートのコースというのは、いろんなことで、いわゆるファインアートと呼ばれているものだけではなくて、まさに心に響くような、いろいろな体験をアートという切り口から感じてもらえたらいいなということで、今年も、実は明日またやるのですが、継続でいま4年目になります。
私の方からこの後のパネルディスカッションにも関わって、今日お二人中心にお聞きしたいことがあるので、アートに関心を持っているビジネス端の人ってどんな感じなのかなというのだけ簡単に、自分で感じていることを書きました。一つはアートのブランディング効果的な、例えば左だったらメセナと呼ばれているものだし、右だとルイビトンが出しているパリの美術館だったりするわけで、こういった、ちょっとアートやってていいよねみたいなそういう感じの関心ですね。これはあると思います。
もう一つがいわゆるマーケットとして、ビジネス型なので、アートのマーケットというとコロナ禍でもバンクシーの絵が28億8千万で売れましたという話だとか、右側のスペインのビルバオのやつは地域活性に美術館をやりましょうみたいな、そんなところに興味ある人もいます。それから、いわゆるイノベーションというので最近はアートシンキングだという感じでいろんな本が出ていまして、私もいっぱい読むんですけれども、面白いのも面白くないのもいろいろありましたという中ですけれど、いろんなのが出て来たり、今はNFTRというのが今年のキーワードになっていますが、テクノロジーとどう結びついてアートを考えるかというあたりで興味関心をお持ちの方もいらっしゃいます。
もう一つは、これは今日お二方とお話してみたかったところで、Wellbeingという言い方が最近出て、以前から心のゆたかさに繋がるようなアートというところで関心を持っている方がものすごい多くなって来ているなという気がすごくしていて、横田さんのお話にも心という話が何度か出ていましたし、それから、傍島さんの話では魂という話があったので、この辺を聞けたらなということで、ガチガチビジネスからアートに戻って来た私の方がお邪魔しているという次第です。
高橋:ありがとうございます。
臼井さんの方から先ほど二人のお話を聞いていただいて、感想や質問があれば外からの目線ということでお伺いできたらと思います。
臼井:横田さんのお話に心を洗う表現が出ていたり、傍島さんのお話では魂だったり、情熱という話は両方から出ていましたし、この後藤野ではどうしてというお話も出てくるとは思うのですが、アートの力というか魅力というか、すでにいくつかお話されているのですが、改めてアートって何がいいんですかと言われた時にどうお答えするのかなというのを聞いてみたいです。
横田:それは作る側としての?
臼井:どちらでも構わないです。人としてというイメージで今聞いてみたんですけど。
横田:自分は作る側ですから、作っている過程そのものがアートでありたいと思います。ですから、設計室であらかじめ決めてしまう現代の作り方というのを非常に嫌うのです。大まかに決めておいて、しかもなるべく生の素材を使えば、料理と同じで、少しずつ変えていかないと最終的にはいいものができない。気まぐれにいろんなことをやっているわけではなくて、いいものというのがゴールにあってですね、美味しいものを食べたいとか、いい音を聞きたいとかそれがあるからこそ予定通りにいかないことがあるのではないかなと思います。それが心の豊かさに繋がるのかなと思います。
臼井:さっき、木の組み合わせの話もすごく印象的でした。まっすぐにしたい時に、まっすぐの木を切って作るのではなくて、少し曲がっていたら反対に曲がっているものを合わせてまっすぐにする。
横田:まさに、スウェーデンの教会なんか天井がこういう材木でうまく組み合わせていて、日本の石垣みたいな感じで教会の屋根が作られています。元々はアートとしてやったわけではなくて、まず木を切って、今のように切るのは手でやるのは大変なのです。無駄な力がかかるから、そんなことをかけるのではなくてとにかくちょっと綺麗にしてあとは選んで合わせていく。それは必然なのです。我々から見ると非常にアーティスティックに見えますけど、それは当時の人たちのやんごとなきというか、本当に必然なんです。その結果、しかも手でやるしかなかったところが、そういう結果を招いたということで、その辺の偶然にそうなる、大元の意図は違うけれど設定ですね、Primitiveな道具しか持っていなければ、そうやるしかないという風なことで、いいものができたというのが、いろいろな場面で、オルガンという大きな楽器で、いろんなところでそういうのが現れるのがわかります。ですから、作る側も、とりあえず機械を返してみようと、そこで何が起こるだろうと、そういう難しい材料を前にして、いろんなことができなければ、こうやるしかない、そこから自然に決まっても、アートになってっちゃうという感じがします。
傍島:僕は好きな言葉で、日本人の天才数学者の岡潔さんという方がいて、その方が人間が最も大切にしなければいけないことはみたいな話で、結構情緒という言葉をたくさん使っていて、情緒ってなんぞやと結構僕の中でアートと情緒って一体化しているところがあって、作品と対峙したりした時に現れる情緒みたいな今ここ感じているみたいな・・・